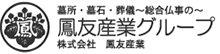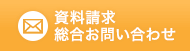「おのじ通信」Vol.502018年5月17日(林編集員)
“お盆提灯を灯す意味ってなに?”
子供の頃、おばあちゃんが「ご先祖さまが帰ってきたよ」と言いながらお線香を上げていたのを思い出しますが・・・
お盆提灯の始まりには諸説あり、鎌倉時代に精霊を迎えるために庭先や屋根の上に高い竿を立て、その先に提灯を付けた高灯籠が始まりと言われています。
光は庶民の必需品であり、仏教の教えでは人々を照らす仏様の智恵を象徴する物として大事にされました。
庶民がお盆提灯を灯すようになったのは、その後ろうそくが普及し始めた江戸時代からと言われています。
お盆提灯の光は、亡くなったご先祖様が迷わず家へ戻ることは勿論のこと、あの世へお帰りの時にも無事に戻られるように目印として灯すものです。行き帰りの道を照らす心遣いなのです。
“提灯を灯しておく期間は?”
7月盆、8月盆ともにお迎えの13日~お見送りの16日まで提灯の明かりを灯します。
ご先祖様をお迎えする「迎え火」は13日夕方から夜まで灯し、日中は消しておく。14日・15日も同様にし、「送り火」となる16日は夕方から夜まで灯し、ご先祖様を送ります。
親戚がお盆供養などで集まる際には夕方から夜の点灯に加え、昼間でも灯しておきます。
基本的には夜中は消しますが、地域や家の習わし、遺族の意向によっては四六時中灯す場合もあります。
最近は電気や一部LEDなどの明かりが増えたため、夜間も長時間灯していられますが、種類により電球が熱を持ち危険なこと、また省エネの面からや夜間に灯りの見守りがいない場合は消しておくのが一般的です。
お盆提灯は時代の流れ、生活環境の変化などで大きさや形、種類も様々です。大切な先祖、故人の道標となるお盆提灯の灯りは、日本の夏の風物詩とも言えるかもしれません。
先祖や故人を偲び、冥福を祈り、今日ある自分を顧みるというお盆の考えは昔から変わらず、感謝の気持ちを込めた供養の証がお盆提灯なのです。
合掌の郷 町田小野路霊園でも5月19日(土)よりお盆提灯をはじめ、様々なお盆に関する商品の展示・販売を行います。ご購入された方には特典もご用意しております。
是非お誘い合わせの上、ご来園ください。
お盆用品展示会
- 日程 5月19日(土)~6月24日(日)
- 場所 合掌の郷 町田小野路霊園 泰鳳閣 大ホール